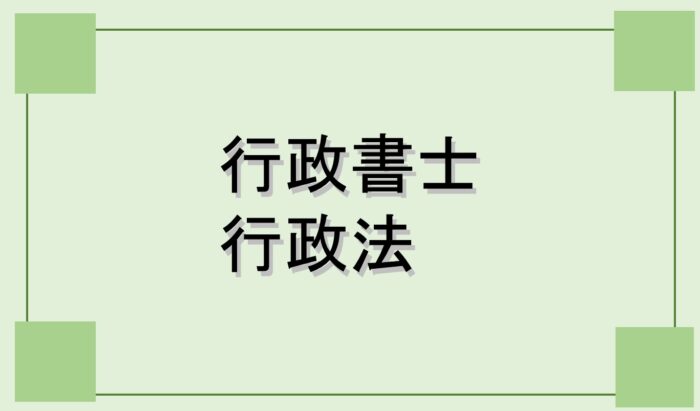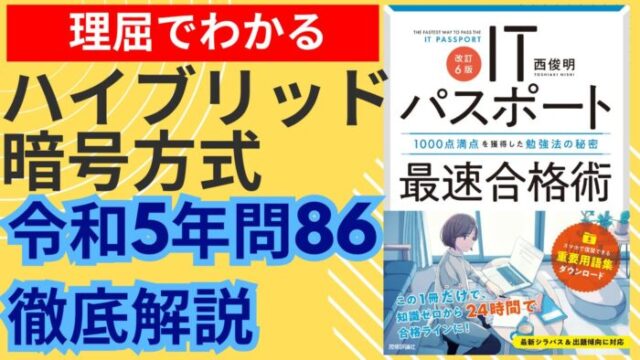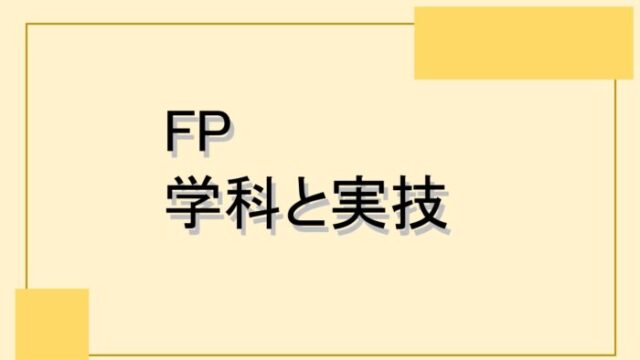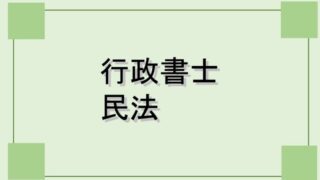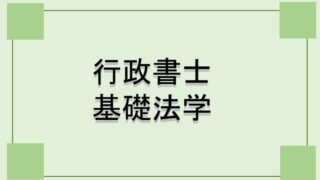「行政」という単語が付いているとおり、行政法は行政書士試験において、もっとも重要な科目の一つです。
しかし、私の周りを見ても、行政法に苦手意識を持っている方は多いようです。
確かに、憲法や民法に比べ、あまり馴染みのない法律です。さらに試験範囲も広く、無味乾燥な暗記中心の科目といったイメージがある点が、多くの方が苦手意識を持つ理由でしょう。
このように少し人気のない行政法ですが、私は好きな科目でした。
何故ならば、
行政法には正しい対策のポイントや勉強方法があり、それを実践すれば、誰でも得意科目にすることができる
からです。
それでは、行政法の対策のポイントや勉強方法とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
以下、分かりやすく説明したいと思います。
なお、行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料【タダ】でプレゼント中です。
無料【タダ】ですので、入手しないと損ですよ。
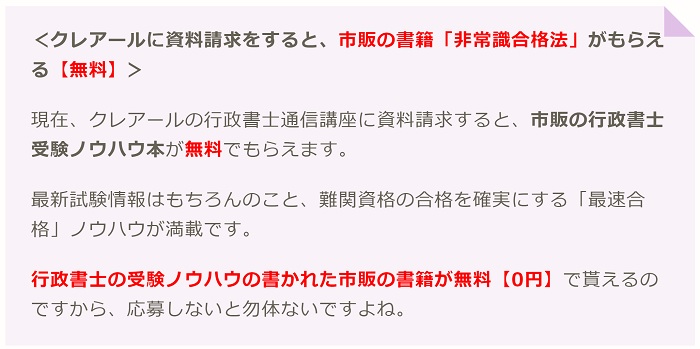
=>クレアール 行政書士試験攻略本(市販のノウハウ書籍)のプレゼントはこちら
.
目次
行政法とは
そもそも、行政法とはどのような法律なのでしょうか?
実は、「行政法」という名の法律はありません。六法全書にも掲載されていないのです。
それでは行政法とは何かというと、「行政に関する法律の総称」というのが正しい説明になります。
ご存知のとおり、我が国は「司法」「立法」「行政」と、三権分立が定められている国です。
「行政」とは、一般的な考え方によれば、「司法と立法以外のもの」ということになります(この考え方を、控除説といいます)。
つまり、司法と立法に関する法律以外は、ほとんどが行政法に分類されるのです。その数、なんと1,000以上。
ひとくちに行政法といっても、非常に多くの法律が関係しているのが分かるかと思います。
行政法の出題範囲
そんな行政法ですが、以下のとおり、大きく3つに類型化できます。
| 行政組織法 | 行政(国や地方公共団体)の内部組織に関する法律 |
| 行政作用法 | 行政が行う活動についての法律 |
| 行政救済法 | 行政の活動の結果、被害や損害を受けた国民などを救済する法律 |
この3つの類型に入る個別法規の例としては、以下のようなものがあります。
| 行政組織法 | 国家行政組織法、地方自治法 |
| 行政作用法 | 行政代執行法、行政手続法 |
| 行政救済法 | 行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法 |
上記のなかの赤字の法律は、行政書士試験の「行政法」の出題の中心となる法律です。
これら5つの個別法規に「行政法の総論」を加えた6つの分野から、行政法の試験は出題されます。
行政書士試験における行政法の特徴は?
ここでは他の科目と比較しつつ、行政法の特徴を見ていきましょう。
行政書士試験の中で配点がもっとも大きい
行政法は行政書士試験の中で、もっとも配点の大きい科目です。
基礎法学:8点
憲法:20点
行政法:76点
民法:36点
商法・会社法:20点
憲法:8点
行政法:16点
行政法:20点
民法:40点
政治・経済・社会:28点
情報通信・個人情報保護:16点
文章理解:12点
上記のとおり、行政法の配点を合計すると、112点となります。行政書士試験は300点満点ですので、行政法だけで試験全体の4割近くを占めることにあります。
※以下は、各科目の勉強法の記事となります。
行政法は、すべての出題形式で出題される唯一の科目
また、行政書士試験には、5肢択一式・多肢選択式・記述式と、3つの出題形式がありますが、
行政法は、これら3つのすべての形式で出題される唯一の科目となっています。
それぞれの出題形式により、対応方法が異なりますので、それを意識した取り組みが必要です。
出題傾向 ~広範囲で細かく出題される
行政法の試験範囲は広範です。しかも、出題されやすい論点・出題されない論点というものが少なく、試験範囲全体から、まんべんなく出題される傾向にあります。
しかも、条文の記述をきちんとおさえていないと解けないような、非常に細かな出題ばかりです。
正直なところ、「テキストをざっと読んで、なんとなく理解した」というレベルでは太刀打ちできません。
各論点を細かくおさえていく必要があります。
難易度 ~過去問からのリピート出題も多く、対応しやすい
広範で細かい論点が多い行政法ですが、一方で、対応はしやすい科目といえます。
条文の内容を元に出題されますから、逆にいえば、条文さえ適切に理解しておけば、高得点も可能な科目です。
さらに、行政法では、過去問からのリピート出題の割合が多くなっています。
5肢択一では、過去問の選択肢がそのまま出題されたり、少し表現を変えて出題されることがよくあります。
また、5肢択一式・多肢選択式・記述式と、異なる形式の過去問から、別の形式に変更して出題されることもよくあります。
出題形式のなかで、もっとも難しいのは記述式ですが、記述式においては、ほぼ、過去に出題された論点からしか出題されていません(5肢択一式、多肢選択式の過去問含む)。
以上のように、過去問対策をベースとして、しっかりと知識を蓄積しておくことにより、高得点も狙える科目といえるのです。
勉強法
それでは、効率的かつ高得点を狙える、行政法の勉強方法についてお伝えします。
①テキストを一通り読み、全体像を押さえる
最初に、細かい点は気にせずに、テキストをざっと読み通します。
このような読み方で、行政法の全体像をつかみます。
多少理解できない点があっても大丈夫。まずは時間を掛けずにテキスト一冊読み切ることが重要です。
②1単元ずつ丁寧にテキストを読み、その単元と関連した過去問を解く
テキストの読み込み2回目では、1回目よりしっかりテキストを読んでいきます。一つの単元(章や節)を読んだら、その部分に対応する過去問を解きましょう。
上記のような学習をするためには、「年度別」よりも「論点別(テーマ別)」の過去問のほうが圧倒的に使いやすいです。10年分以上は掲載されているものが良いです。
③不正解の問題等にマークをつけ、復習する
問題を解答して採点すると、、それぞれの問題は「迷わず正解」「自信が無かったが正解」「不正解」のいずれかに分かれます。ここで
・自信が無かったが正解 → △
・不正解 → ×
のようなマークを付けて、それらを復習します。
④過去問を解き終えたら、×と△の問題を再び解く
過去問をすべて解き終えたら、ふたたび最初のページに戻り、×と△の問題だけ解き直します。
⑤×と△がすべて○になるまで、過去問のリピートを続ける
×と△の問題については、解き直すなかで「自信を持って正解」できた問題は、その時点で終了。すべてが「自信を持って正解」できるまでリピートします。
以上が最短で仕上げるための勉強法となります。
試験対策 ~勉強のポイント
それでは、試験対策上、どのような点を気をつけて勉強すればよいのか、ポイントを見ていきましょう。
漠然と「行政法」と捉えず、どの法規から出題されているのかを意識する
前述のとおり、行政法は以下の個別法規および総論から出題されます。
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 地方自治法
問題を解く際には、「いま解いている問題は、●●法(または総論)に関する論点だ」
と意識することが必要です。
「行政法が苦手」という人の多くは、漠然と行政法を捉えていることが多いと感じます。
ひとくちに行政法と言っても、それぞれの法は目的も違えば、勉強法も異なります。
たとえば、国家賠償法と地方自治法の目的を理解できていれば、それぞれに関する問題の理解も変わってくるはずです。
問題を解く際には、ぜひ、それぞれの法律を意識しながら、取り組むようにしてください。
過去問を重視
前述のとおり、行政法では、過去問からのリピート出題が多くなっています。
つまり、行政法の攻略法の考え方は、
いかに過去問を上手く活用して、効率よく知識を定着させるか
ということになります。
前述の勉強法で説明した、「△や×の過去問」がなくまるまで、徹底的に過去問を潰して欲しいと思います。
おすすめテキスト・六法・判例集・アプリなど
https://gyousei-fight.com/gyousei-dokugaku-text/
https://gyousei-fight.com/gyousei-osusume-6-hou/
https://gyousei-fight.com/gyousei-hanreisyu/
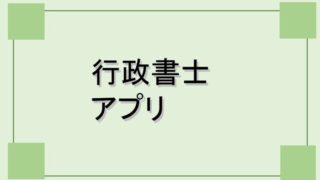
初学者の方には、マンガ版の参考書もオススメです。
https://gyousei-fight.com/gyousei-manga/
行政法の試験対策のポイントと勉強方法 <まとめ>
ここでは、広範かつ細かい出題のため、苦手意識を持つ人の多い行政法について、対策のポイントや勉強法をお伝えしました。
行政法の攻略のポイントは、何と言っても「過去問をうまく活用すること」にあります。
ぜひ、この記事で説明した勉強方法を参考にして、効率のよい行政法対策を実践してみてください。
また、時間のない社会人の方などは、スキマ時間にスマホで学習できる行政書士オンライン通信講座なども検討してみてください。