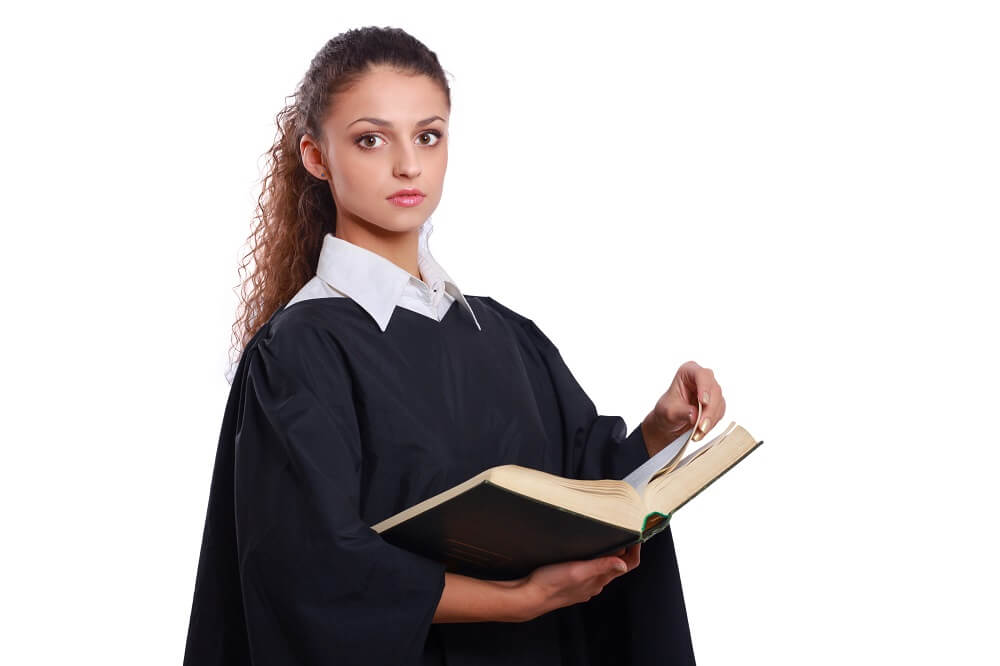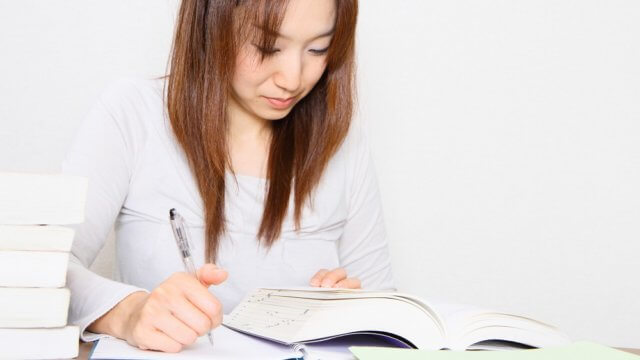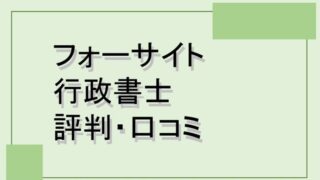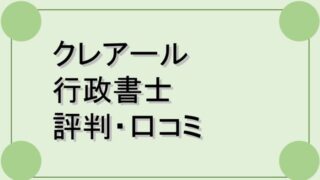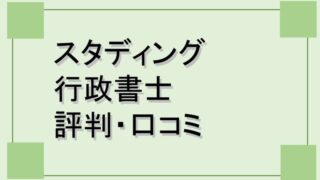今回は、行政書士試験の基礎法学のポイントや勉強方法についてお伝えします。
基礎法学とは、民法や行政法などの個別の法を研究するのではなく、様々な法に共通する性質を研究する学問のことです。
行政書士試験においては、基礎法学の配点は最も小さいため、「基礎法学は捨てる」と考える受験生も少なくありません。
確かに、基礎法学に使う時間があれば、行政法や民法などを勉強したほうがよい、という考え方は正しいです。
とはいえ、最初から完全に捨てる、というのも、また、もったいない気がしますよね。
この記事では、行政書士試験の基礎法学について、最小限やっておくべき対策や勉強法を紹介しています。
ぜひチェックしてみてください。
基礎法学とは
基礎法学では、法律全体に共通する性質を研究する学問です。
行政書士試験の基礎法学では、具体的には、以下のような内容が問われます。
法の原理
法の効力
法の分類
法の解釈
法律用語
さらに、厳密には「基礎法学」の分野に入らないものの、紛争解決制度についても、よく出題されます。具体的には、以下のようなものです。
裁判制度
裁判員制度
民事訴訟
裁判外紛争処理手続き
行政書士試験における基礎法学の特徴
それでは、他の科目と比較した、基礎法学の特徴を見ていきます。
行政書士試験の中で配点が300満点中、8点しかない
基礎法学は行政書士試験の中で、もっとも配点の小さい科目です。
- 基礎法学(2問):8点
- 憲法(6問):28点
- 民法(11問):76点
- 行政法(22問):112点
- 商法(5問):20点
- 政治・経済・社会(7問):28点
- 情報通信・個人情報保護(4問):16点
- 文章理解(3問):12点
上記のとおり、300満点中、配点はわずか8点。
ほとんど合否に影響しない配点ですので、必須な対策のみを行い、行政法や民法の勉強のア配分を大きくするのが良いでしょう。
※なお、それぞれの科目の勉強法については、下記の記事をご覧ください。
出題傾向 ~基礎法学は5肢択一式、広範囲で難問も多い。
5肢択一式
基礎法学は5肢択一式で2問出題され、各4点のため、2×4=8点の配点です。
難易度 ~広範囲から出題され、難問も多い。
基礎法学は、行政書士試験の冒頭、第1問と第2問に出題されます。
そして、過去の傾向を見ると、
第1問に難問が出題されることが多い
という特色があります。
これは、受験生の立場になって考えると、心臓にとても悪いことが分かる、と思います(笑)
受験生の誰もが、試験開始直前は緊張しています。
そして試験開始の合図があると、急いで問題用紙のページをめくります。
そこには、第1問・基礎法学の問題文が書かれてあるわけですが・・・、過去、難問奇問のケースが多かったのです。
あたかも、受験生をけん制するような、趣味の悪い行為に思えて仕方がありません・・・(笑)
ですので、もし今後、あなたが行政書士試験を受験する際、第1問がまったく分からなくても、
第1問が難しいのは、試験委員の仕掛けたワナだから気にしない!
という気持ちで取り組んで欲しいと思います。
ちなみに第2問は、第1問が難しい分、取り組みやすい問題が多い印象です。
基礎法学の得点目標
基礎法学は2問中1問得点できれば十分です。
試験対策のポイントと勉強方法
他の科目の勉強に役立つ部分を、きちんと押さえる
基礎法学では、法律全体に共通する性質や知識を学びます。つまり、憲法・民法・行政法などを勉強する際に、覚えておいた方がよい知識なども学ぶのです。
たとえば、それぞれの法律の条文は「条、項、号」「本文、ただし書き」「前段・中段・後段」と呼ばれる部分から構成されています。
これらの条文を構成する要素を正しく理解しておけば、条文を読むときに役に立ちますよね。
また、「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」など、普段はあまり意味の違いを意識しない用語でも、法律用語として使う場合には、それぞれ異なる意味があるのです。
以上のようなことは、行政書士テキストの基礎法学のところで説明してありますので、税所に一通り読んで、他の法律科目の勉強の際に役立てましょう。
時事テーマに関心を持つ
基礎法学では、時事的な法律知識が出題されることもあります。最近では、裁判員制度について出題されました。
このような出題では、特に基礎法学向けの勉強をしていなくても、該当する新聞記事やニュースに対し、関心を持って接しておくだけで得点できることがあります。
普段から法律関連のニュースに敏感になることが重要です。
過去問は一通り見ておく
基礎法学は毎年2問しか出題されないため、過去問も多くはありません。
「どのような出題のされ方をするのか」
押さえておくために、過去問にも一通り当たっておきましょう。
「2問しかないから、一切勉強せずに捨てる」という考え方は大間違いです!
この記事に書いたことだけを実践するだけで、最低でも1問を獲得できる確率は飛躍的に上がります。
後々、ギリギリの当落線上で「泣き」を見ることのないよう、ぜひ取り組んでみてください。
おすすめテキスト・六法・判例集・アプリなど
私のおすすめ一覧です。気になるものがありましたら、どうぞ!

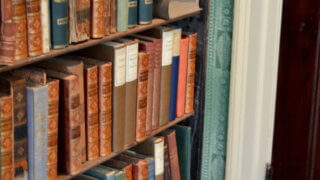
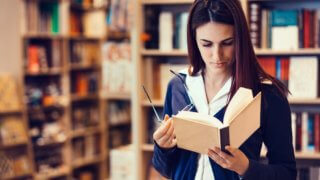

法学初心者には、漫画版もオススメですよ。

行政書士 基礎法学の試験対策のポイントと勉強方法 <まとめ>
ここまで見てきた基礎法学ですが、行政書士試験の出題分野のなかで、もっとも配点が小さいので、ポイントを押さえて、5割の得点を獲得すれば十分です。
ぜひあなたにも、効率よく基礎法学に対処して欲しいと考えています。
| この記事の監修者 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 , 2級FP技能士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |