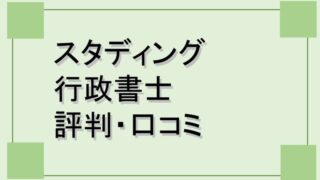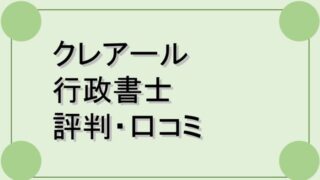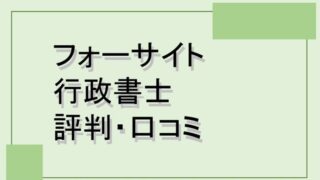行政書士の開業資金はどのくらいなの?
行政書士は社会保険労務士とは違い、特定の会社に属して企業内で仕事に活かすことはできません。
つまり、行政書士の仕事をするには、専業・副業に関わらず、資格登録をして開業する必要があります。
そこで、「行政書士の開業費用はどのくらいなの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
頑張って勉強をして行政書士の試験に合格しても、あまりにも開業資金が高いと戸惑ってしまいますよね。
行政書士の資格を活かして独立開業しても、すぐに顧客を獲得できるわけではありません。
1年間くらいの期間は食えない点を加味すると、それなりの開業資金を用意する必要があります。
この記事では、行政書士の開業資金を項目別でまとめてみました。
※なお、行政書士の独立開業の流れについて詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

行政書士会への登録料
行政書士の開業資金の中でも、行政書士会への登録料がかなりの金額になります。
行政書士試験に合格しても、行政書士会に登録しないと顧客に対して業務を提供できません。
つまり、行政書士として独立開業するに当たり、登録料は絶対に必要な資金です。
行政書士会への登録料は、下記のようにトータルで30万円程度がかかります。
- 入会金として20万円程度
- 登録手数料として25,000円程度
- 3ヵ月分の会費として2万円程度
- 登録免除税として3万円程度
独立して間もない行政書士はすぐに稼ぐことができないため、30万円程度の登録料は大きな負担です。
しかし、行政書士会への登録には次の4つのメリットあり!
- 顧客に対して行政書士としての仕事ができるようになる
- 会員向けの研修会や勉強会、セミナーの案内が送られてくる
- 法改正に伴うマニュアルなどの情報を手に入れられる
- 同じ行政書士として働く人と繋がって人脈を広げられる
行政書士として活躍するには実務経験を積むのが必須条件ですので、登録料の負担は仕方がありません。
一方、行政書士試験に合格しても、すぐに開業しない方は、登録を先延ばしする手もあるでしょう。
※行政書士の登録の詳しい手続きなどについては、下記の記事を参考にしてください。

毎月の家賃(敷金・礼金)
事務所を借りて開業する行政書士は、毎月の家賃がかかります。
テナントによっては敷金や礼金も発生しますので、忘れてはならない開業資金ですね。
場所や広さによって異なりますが、行政書士事務所の賃貸費用は10万円~50万円程度が目安と幅があります。
独立時には、なるべく家賃を抑えたいものですが、顧客に来訪してもらうためにはアクセスの良さも気になるので、どの辺で折り合いとつけるのかが難しいところです。
独立開業すると行政書士事務所の家賃だけではなく、電気代などの光熱費もかかりますので注意しましょう。
業務で使う備品
行政書士の業務で使う備品は、それなりに大きな金額になります。
行政書士の仕事をこなすに当たり、具体的に何を用意すべきなのか見ていきましょう。
- 固定電話やFAX機器
- コピー機(インクジェットプリンタ)
- デスクや椅子
- パソコンやインターネット回線
これらの備品の費用をトータルで考えると、30万円近くの出費になります。
通信機器の中でも、行政書士の業務を行う際に電話回線とFAX機器は必須です。
「プライベート用のスマホがあれば良いのでは?」とイメージしている方はいませんか?
しかし、顧客に対して失礼のないように接する必要がありますので、自宅の電話回線やスマホと行政書士事務所の電話回線はわけるべきです。
全ての備品を新品で購入するとかなりの金額になりますので、机や椅子は中古品で我慢して経費を節約してください。
営業で必要な広告費
営業で必要な広告費も、行政書士の開業資金の中に含まれます。
ただ黙っているだけで仕事が舞い込んでくることはありませんので、行政書士は自分から積極的に営業して顧客を獲得する努力をしないといけません。
例えば、ネット営業で集客を図る予定であれば、「ホームページ作成ソフト」「レンタルサーバー」「ドメイン使用料」などの費用がかかります。
広告費に資金を費やし過ぎると経営が圧迫しますし、逆に削減しすぎるとお客さんが減りますので難しいところです。
正解不正解はありませんが、トータルの自己資金と照らし合わせてどのくらい広告費に費やすのか考えましょう。
※行政書士の営業方法について詳しくは、下記の記事も参考にしてください。

生活費
上記でも軽く解説しましたが、行政書士として開業してもすぐに稼ぐことはできません。
士業の多くは知名度や信頼度が上がるにつれて仕事の量が増えますので、最初は無収入で耐えないといけない時期が出てきます。
「仕事が受けられない=全く稼げない」というケースは珍しくありませんので、行政書士事務所の開業資金の中に生活費も入れておきましょう。
「無収入期間が長くなって経営できない…」といった事態を防ぐには、生活費をしっかりと貯金しておくべきです。
多く見積もって1年分の生活費や広告費などのランニングコストがあれば、安心して行政書士の資格を活かして独立開業し、業務をこなしていくことができますよ。
「稼げない」「利益がない」と焦っても仕方がありませんので、行政書士として独立開業する方は地道に営業活動を続けましょう。
行政書士が自宅で開業するメリット!
行政書士の開業資金は、トータルで100万円以上かかることもあります。
開業資金に加えて生活費を加味すると、もっとお金を貯蓄しておかないといけません。
そこで、開業資金の負担を少しでも抑えたい行政書士は、事務所を借りるのではなく自宅で開業しましょう。
自宅を事務所代わりにして、行政書士の業務をこなしている方はたくさんいます。
以下では、行政書士が自宅で開業するメリットをいくつか挙げてみました。
- 敷金や礼金、毎月の家賃を節約して開業資金を抑えられる
- 事務所への移動時間が発生しないため、通勤時間を短縮できる
- 早朝でも深夜でも自分の好きなタイミングで仕事ができる
- 事務所で使う家賃や光熱費を経費として計上できる(節税効果が見込める)
開業資金の負担が減るだけではなく、自宅開業は通勤時間の短縮や節税効果などのメリットもあります。
最初は自宅の一室で開業し、ある程度軌道に乗ってきたら行政書士事務所を持てば良いのです。
ただし、行政書士が自宅事務所で開業するに当たり、「自宅の住所がバレる」「人を雇うのが難しい」「顧客からのイメージが低下する」といったデメリットもありますので気をつけてください。
行政書士の資格を活かして開業して食えない時期にバイトするメリット!
行政書士は一生ものの国家資格ですが、次の理由で「食えない」「稼げない」と言われています。
- 社会保険労務士とは違い、企業に所属して業務を行うのは認められていない
- 行政書士の人数が増えすぎて、1人当たりの仕事の量が減っている
- 将来的にAI(人工知能)の開発が進んで仕事が奪われるリスクがある
行政書士の資格を活かして開業しても、利益を出せなくて廃業の道を辿る方は少なくありません。
事務所を運営するにはそれなりの費用がかかりますので、行政書士の資格を活かして開業して食えない時期にバイトするのは選択肢の一つ!
行政書士が兼業でバイトするに当たり、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
- 固定収入を得ることができれば、顧客を獲得できなくても生活費の心配がなくなる
- 士業系事務所でアルバイトをすれば、その経験を日頃の業務に活かせる
- 接客業を選択すれば、コミュニケーション能力を磨くことができる
行政書士の資格を活かして開業しても1年間くらいは十分な収入を得られないこともありますので、アルバイトで生活費を稼ぐ方法も検討すべきですね。
本業に役立つバイトであれば一石二鳥ですので、何の仕事が良いのかじっくりと考えてみてください。
行政書士として開業して食えない時期にバイトするデメリット…
行政書士の仕事が無収入の時に、バイトをしていれば金銭面での不安がなくなります。
しかし、行政書士として独立開業して食えない時期にバイトするに当たり、次のデメリットがありますので注意しないといけません。
- 短期的に見ると、それなりの収入が見込めるため、バイトに精を出し過ぎて本業が疎かになる可能性がある
- バイトをしても行政書士としての仕事の顧客を獲得することはできない
- 行政書士事務所の補助者のバイトはチラシ配りや来客対応が多く、スキルアップは見込めない
開業資金を貯める目的で行政書士がバイトをするのはOKですが、本来の目的は事務所の収入を安定して本業だけで生活することです。
行政書士事務所の運営をそっちのけにして、バイトに明け暮れる日々を送っていては意味がありません。
そのため、行政書士と兼業してバイトするのはなるべく控えましょう。
行政書士として開業したら速やかに業務経験を積もう!
行政書士は試験に合格すればそれで終わりではありません。
独立開業した後はやるべきことがたくさんありますので、アルバイトに精を出すのはやめた方が良いですね。
そこで、行政書士として開業した後は、速やかに事務所の経営を軌道に乗らせるためにも次の点を意識しましょう。
行政書士に限った話ではないものの、士業は営業力が稼ぎに大きな影響を与えます。
積極的に営業をしながら実務経験を積むことで、行政書士として開業して食えるようになるわけです。
最初は上手くいかないこともあって挫折しやすいのですが、行政書士の資格は今後もビジネスチャンスが多く見込まれますので、業務経験を積んでスキルアップする努力をしてみてください。
まとめ
以上のように、行政書士として独立開業するに当たって、どのくらいの開業資金が必要なのかおわかり頂けましたか?
自宅を事務所代わりに使うことはできますが、「行政書士会への登録料」「毎月の家賃」「備品代」「広告費」「生活費」など開業には様々な出費がかかります。
だからと言ってバイトと兼業するのはあまりおすすめできませんので、行政書士事務所を軌道に乗らせるためにも速やかに業務経験を積むことが大切です。
【補足】行政書士試験の概要・試験制度について
ここからは、行政書士試験の概要や試験制度についての情報を記載します。
行政書士試験の受験日や受験料
受験日や時間帯、受験料は以下のように定められています。
試験日:毎年11月の第2日曜日(毎年1回)
時間帯:午後1時~午後4時まで
受験料:10,400円(地震や台風で試験を実施しなかった場合を除き返還しない)
1年間に1回しか実施されていない試験ですので、合格するには前もってしっかりと準備するのが大事です。
行政書士試験の内容/合格基準
試験の内容や科目は、大きく次の2つにわけることができます。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題)
- 行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題)
法令等は択一式及び記述式で配点は244点、一般知識等は択一式で配点は56点です。
行政書士試験の合格基準は、「法令等科目の得点が満点の50%以上」「一般知識等科目の得点が満点の40%以上」「試験全体の得点が満点の60%以上」で、全てを満たした時に合格できます。
行政書士試験の受験手続きの流れ
以下では、受験手続きの方法や流れについてまとめてみました。
- 試験案内の掲載・配布(7月の2週辺りからホームページに記載)
- 受験申込みの受付(受験願書と顔写真画像を登録)
- 受験票の送付(毎年10月中旬~下旬辺り)
- 試験の実施(毎年11月の第2日曜日)
- 試験結果発表・合否通知書の送付(受験者全員に合否通知書を送付)
- 合格証の送付(毎年2月中旬~下旬辺り)
受験手続きはインターネットではなく郵送も受け付けていますので、詳細は一般財団法人行政書士試験研究センターのWebサイトをご覧になってください。
参考:https://gyosei-shiken.or.jp/doc/abstract/flow.html
受験願書・試験案内の配布と請求方法
受験願書や試験案内の請求方法は、次の2つから選ぶ形になります。
- 窓口で受け取る
- センターに郵便で請求して郵送してもらう
配布されている期間はあらかじめ決まっていますので、事前に確認しておきましょう。
行政書士試験の受験資格
行政書士試験の受験資格は、「○○○が条件」とは特に設定されていません。
「年齢」「学歴」「性別」「国籍」に関係なく、誰でも受験できる国家資格です。
しかし、行政書士試験に合格しても、都道府県の行政書士会に入会して登録しないと行政書士を名乗って業務をすることができません。
この点に関しては、行政書士法第2条の2の「欠格事由」で、下記に該当する者は行政書士になる資格を有さないと決められています。
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられた者で3年が経過しない
- 公務員で懲戒免職の処分を受けて3年が経過しない
- 登録の取消しの処分を受けて3年が経過しない
- 業務の禁止の処分を受けて3年が経過しない
- 懲戒処分により弁護士会から除名された
行政書士として働くに当たり、試験に合格すれば良いという単純な話ではありません。
行政書士試験の勉強時間を他の資格と比較
個人の学習方法によって変わりますが、行政書士試験に合格するには500~800時間程度の勉強時間が必要です。
他の資格との比較は以下のとおり。
- 弁護士(予備試験):6,000時間
- 公認会計士:3,000時間
- 司法書士:3,000時間
- 税理士:2,500時間
- 不動産鑑定士:2,000時間
- 中小企業診断士:1,000~1,200時間
- 社会保険労務士:1,000時間
- 行政書士:500~800時間
- 宅地建物取引主任者:400時間
- 日商簿記2級:250時間
同じ法律関係の司法書士や税理士と比べてみると、行政書士試験は短い期間で合格できます。
行政書士試験の合格に必要な勉強時間について、下記に詳細をまとめてあります。よろしければ、そちらも参考にしてください。
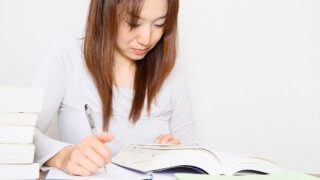
行政書士試験の難易度(偏差値のランキングから見た難易度)
以下の資格試験の偏差値は非公式なものです(そもそも資格試験に正式な偏差値はありません)。
ただ、非公式と言えども、多くの資格の難易度を比べるには便利ですから、参考程度にご覧ください。
- 偏差値70:「裁判官」
- 偏差値68:「検察官」
- 偏差値67:「弁護士(予備試験)」
- 偏差値66:「弁護士(ロー卒)」
- 偏差値65:「公認会計士(全科目一括合格)」「医師(国公立卒)」
- 偏差値64:「弁理士(免除なし)」「公認会計士アクチュアリー」「司法書士」「税理士(5科目受験免除なし)」
- 偏差値62:「弁理士(選択免除)」「1級建築士」「不動産鑑定士」
- 偏差値61:「税理士(3科目受験2科目免除)」「通訳案内士」
- 偏差値60:「社会保険労務士(社労士)」「土地家屋調査士」「中小企業診断士」「ITストラテジスト」
- 偏差値59:「システム監査技術者」「獣医師」「行政書士」「国税専門官」
- 偏差値56:「測量士(受験取得)」「マンション管理士」「1級FP技能士」
- 偏差値55:「電験3種」「英検準1級」「電気通信主任技術者」「エネルギー管理士」
- 偏差値52:「管理栄養士」「社会福祉士」「宅建」「管理業務主任者」
この表で見る限り、行政書士の難易度は、難関国家資格全体のなかで、中程度~やや易しい、という位置づけと考えることができます。